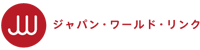インバウンドブログをリニューアル。題して「北関東のインバウンドを10倍にしよう!」!毎週月曜夕方更新でお届けいたします。今回はなぜこのコロナ禍においてインバウンドブログを再開することにしたのか、社長の宮地アンガスとスタッフ山内が対談しました。

いまさら聞けない「インバウンド」の意味とは? 北関東にとってなぜ重要なの?
「インバウンド」という言葉をニュースなどで聞いたことがありますか?
観光と関連するトピックでは、インバウンド客、インバウンド対策、インバウンド観光、インバウンド産業など、インバウンドを使った様々なフレーズが使われています。
「インバウンドは訪日外国人に関する事かな?」となんとなく思っている人も多いのではないかと思います。
そこで「インバウンドの意味」や「今後日本のインバウンド観光の発展」を深く見ていこうと思います。
「インバウンド」の意味とは?
辞書でインバウンドという言葉を引くと、
インバウンド=入ってくる
という意味があるとわかります。
「自分たちの方に向かって近づいてくる」
そのようなイメージです。
例えばマーケティング用語でも「インバウンドマーケティング」という言葉がありますが、これは広告をうって宣伝するのではなく、関心を持ったお客様が、ネット検索などで自分たちの方に近づいてくるようにするマーケティング手法という意味があります。
また旅行用語としてインバウンド観光客というと「私たち日本に向かって近づいてくる観光客」のことなので、海外から日本を訪れる訪日観光客という意味があるのです。
さらに、英語化や免税店整備などの訪日外国人の対策をインバウンド対策、おもてなしやイスラム客の対応をインバウンド対応、訪日外国人に関わるすべての業界をインバウンド産業などと呼びます。
インバウンドは向かってくると言う意味ですので、日本から見るとインバウンド観光客は訪日外国人ですが、アメリカからなど他の国や地域から見たインバウンド観光客は、国外からそこの地域に観光に来る人のことを指すのです。
では、アウトバウンドは?
インバウンドの意味がわかったところで、対義語の「アウトバウンド」を考えてみましょう。
インバウンドは、入ってくるという意味ですので、
アウトバウンド = 出て行く という意味になります。
日本から出て行くというと、貿易かな? 輸出かな?と思ってしまいやすいのですが、訪日旅行(インバウンド)の対義語として使われる場合、アウトバウンドは輸出の事ではなく、旅行やビジネスで「日本から外国に旅行で出て行く(人たち)」を指すのです。
インバウンドの政府目標
観光・旅行用語としての「インバウンド」が、ニュースなどで聞かれるようになったのは、ほんの数年前からです。
その理由は、日本が国として訪日旅行の誘致に本格的に力を入れ始めたのが、2000年以降になってからだからです。当時の小泉総理が2003年にビジット・ジャパン事業(VJ事業)を開始され、その時はじめて「訪日旅行者 年間1,000万人」という目標が立てられました。
2013年に「訪日旅行者 年間1,000万人」を達成(訪日客 1036.4万人、旅行消費額は1兆4168億円)し、この年からインバウンド観光が急に勢いを増します。
さらには2014年1月、観光立国推進閣僚会議にて、安倍首相が「2020年に向けて、2000万人の高みを目指していきたいと思います。」と発言したことで、「2020年までに、訪日旅行者 年間2,000万人」という新たな目標が設定されました。
ところが、ビザの緩和、免税制度の改革、円安などが追い風となり、2年後の2015年に訪日旅行者が1,974万人(旅行消費額は3兆4771億円))を達成し、年間2,000万人の早期達成が確実になりました。
そこで2016年3月、政府は、訪日旅行者(インバウンド旅行客)の目標を下のように新しくしたのです。
「2020年までに4,000万人、旅行消費額 8兆円」
「2030年までに6,000万人、旅行消費額 15兆円」
訪日旅行者数の推移と目標
訪日外国人消費額の推移と目標
2016年にたてられた目標の特徴は、目標人数が大幅に増えただけではありません。
旅行消費額を数値目標にしたことが、非常に重要なのです。
いくら訪日旅行客が4,000万人、6,000万人に増えても、観光地が疲弊しては意味がありません。
日本の地方にとって、しっかり収入を得る手段としての「観光立国」を目指すことが重要なのです。
発展するインバウンド(1.0, 2.0, 3.0...)
インバウンド1.0、インバウンド2.0、インバウンド3.0 …という考え方を聞いた事があるでしょうか?
これらは、J.I.S. (ジャパン・インバウンド・ソリューションズ)の中村社長が講演でよくお話しされるインバウンドの各ステージですが、インバウンドが今後日本(特に地方)にどのような経済的好影響を与えるか、または、インバウンド対策を早めに取り組む必要性を知るのに役に立つので、紹介したいと思います。
インバウンド1.0 (2003年4月〜):
2003年に小泉純一郎総理(当時)が「観光立国懇談会」を主宰し、ビジット・ジャパン事業が開始される。この時期から本格的にインバウンド観光客の誘致(インバウンド1.0)が始まります。
インバウンド2.0 (2014年10月〜):
免税制度が2014年10月に大きく改定され、消耗品も新しく対象となる。さらには、免税のための最低購入金額が5,000円に引き下げられる(2016年)。あわせて、東南アジア諸国向けにビザが大幅に緩和、日本に旅行に来る事が容易になる。同時に円安要因も加わり、東南アジアからインバウンド観光客が爆発的に増大、2016年には、世界から2,400万人が日本を訪れた。
インバウンド3.0 (2020年7月〜):
2020年に東京オリンピックが始まると同時にインバウンド3.0のステージへ。これまでインバウンドに関係がないと思っていた自治体もインバウンドの可能性に気がつき、地方創生の手段として、全都道府県1,718市町村がインバウンドに取り組む時代になる。
訪日旅行者年間4,000万人、年間消費額8兆円、地方の外国人延べ宿泊者数7,000万人泊。
インバウンド4.0 (2030年ごろ〜):
訪日旅行者年間6,000万人を受け入れ、世界一の観光立国へ近づく。インバウンドが多くの地方にとって重要な収入源となる。
訪日外国人年間消費額15兆円、地方の外国人延べ宿泊者数1億3,000万人泊。
まとめ
本日のブログでは、旅行用語としての「インバウンド」の意味と、日本のインバウンドの今後について解説しました。
文中のグラフでもわかるように、訪日観光客は毎年2桁の伸びを示しており、地域経済に落ちるお金も毎年伸びております。政府は13年後の2030年までに、現在の4倍のインバウンド消費額(3.7兆円→15兆円)を目標にしています。しかも、大都会や有名観光地への集中から、地方創生の手段として全国の地方にインバウンド客が流れるような観光誘致を推し進めています。
今後、少子高齢化が急速に進む北関東のような地方にとって、インバウンドは救いの手であり、今すぐに取り掛かるべきトピックなのです。
地方のインバウンドについて、〈「インバウンド公共戦略塾 」で学んだ5つのポイント 〉〈「成功するインバウンド戦略」に必要な3つの要素とは?〉という2つの記事も書いておりますので、ご興味がありましたら、ぜひご覧になってください。
最後に、インバウンド観光の誘致に関するお悩みやご相談ごとがございましたら、スカイプでコンサルテーションなども行っております。どのようなことでも、ぜひ弊社ジャパン・ワールド・リンクまで、お気軽にご相談ください。

ブログ作成者:宮地アンガス
ジャパン・ワールド・リンク代表。栃木県の田舎町育ち。現在英国・ロンドンを拠点として「世界から北関東へ。北関東から世界へ。」をモットーに、日本・北関東のインバウンド及び海外進出を支援中。
毎週月曜日に希望者全員に無料メルマガを発行(詳細はこちら)。